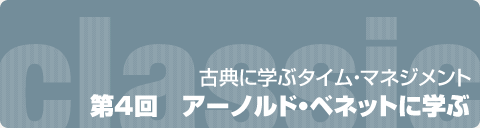今月の「古典に学ぶタイムマネジメント」は、アーノルド・ベネットの『自分の時間』(三笠書房)からの出典です。日本ではあまり有名ではありませんが、本国イギリスの文芸評論家が「20世紀イギリス最大の小説家」と称するほど実力を認められた作家です。
本書は100年以上前の作品ですが、今なお読み続けられているのは、どれだけテクノロジーが発達しようが、時間に関する変わらない原則がいつの時代でも作用する証でもあるようです。
やりたいことをやっていないという。まとわりついて離れないあの日々の焦燥感から開放してくれるすばらしい秘訣を教えてくれるものと期待しているに違いない。
ところが、わたしはそんな素晴らしい秘訣を発見しているわけではない。発見したいとも思わないし、他人が発見してくれるものと当てにもしていない。そんな秘訣は発見できるわけがないのだ。
―中略―
実際のところ、楽なやり方、王道といったものは存在しないのだ。メッカへの道は非常に険しいのだ。そして、何よりも悪いことは、結局そこへは決してたどりつけないことだ。
24時間という与えられた時間のなかで、充実した快適な一日を過ごせるように生活を調整する際に心得ておくべき最も重要なことは、そうすることがいかに至難の業であるか、そのためにいかに多くの犠牲を払い、倦まずたゆまず努力しつづけなければならないかを、冷静に悟ることである。このことは、声を大にして協調しておきたい。
本書では、そういった努力の一貫として、ベネット氏の時間を有効に活用するために、通勤時間や夕食後の時間の使い方や新聞の読み方など工夫を紹介しています。
「7つの習慣」で述べられているように、農作物を一夜にして収穫することなどできない。畑を耕し、種をまき、水をやり、肥料をやらない限り、大きな収穫を得ることはできません。こうした「農場の法則」は、すべての世界に通じるということであり、「努力をしつづけなければならない」原則です。
時間は規則正しく一定して与えられるわけではあるが、この点に関して、とりわけいつも有難いと思うのは、時間というのは前借して浪費することができないということである。
来年の時間や明日の時間、今から一時間後の時間も、手付かずであなたのために取っておかれているのである。あなたが今までの人生で時間を浪費したことなど一度もなかったかのように、完全に手付かずの状態で取っておかれているのである。
これはたいへん喜ばしい、元気づけられる事実である。その気になればいつからだって新規まき直しができるわけである。だから、来週まで待ったりするのは、いま、明日まで待つことすら何の意味もないことなのだ。
「あなたのために取っておかれている」という表現はとてもユニークです。この先の時間をどう使うのかが時間管理の基本的な考え方ですが、取っておかれているのであり、前倒しで使うことはできないという表現は、時間に対するパラダイムが変わります。
たとえ、1日、1週間、1年。あるいは、これまでの人生を浪費したとしても、我々には「来年の時間や明日の時間、今から一時間後の時間も、手付かずであなたのために取っておかれている」のですから。
そしてこう述べています。「その気になればいつからだって新規まき直しができる」。彼の言うとおり、人生をより充実させるために、今日から毎日をより充実させていけばよいのです。
最後にマイケル・アルスシュラーの言葉を紹介しましょう。
「悪いニュースは時間が飛んで行くということ。良いニュースはあなたがそのパイロットだということだ」 時間をどのように活用するか、その裁量を持っているのはあなた自身なのです。